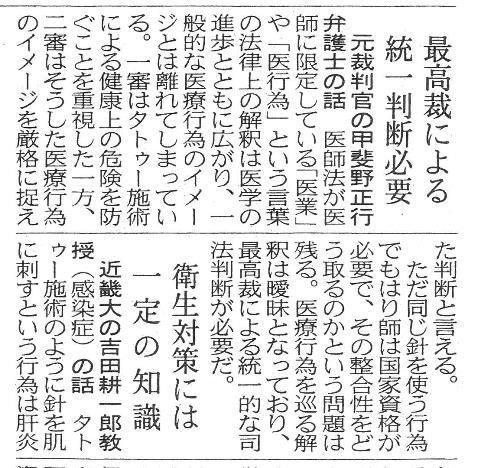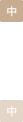「刺青彫り師・逆転無罪・高裁判決」
2018.11.15|甲斐野 正行
平成29年の私のブログで紹介しました、医師免許のない彫り師が女性3名に刺青をしたことが、医師法17条違反に当たるとして起訴され、一審で有罪判決を受けた刑事事件の控訴審判決が、昨日(平成30年11月14日)ありました。
報道によりますと、大阪高裁(西田真基裁判長)は、刺青を入れる行為の身体への危険性は認めつつも、医療に関連した行為ではなく、医師法17条が医師に限定した医療行為には該当しないなどとして、無罪判決を言い渡したということです。
昨年のブログで述べましたように、医師法17条の「医業」、その中身としての「医療行為」は、もともとは単に病気や怪我を治すという本来的な治療行為を意味していました。しかし、医学の進歩により、そうした治療行為からはみ出すが、その関連の行為として、輸血や美容整形、移植等のような行為も技術的に可能になってきました。そこで、これらも医師に限定しないと、国民の身体・健康の安全を守れないという観点から、「医療行為」の意味は次第に膨らんできて、「医師の医学的判断・技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼすおそれのある一切の行為をいう」というものと理解するのが通説的見解となっていました。これは、そういう定義付けをしないと、医学の進歩により今後も範囲が広がっていくであろう医療行為をカバーできないという悩みでもあったわけです。
一審の大阪地裁は、針を皮膚に突き刺して色素を注入する行為は『皮膚障害やアレルギー反応、ウイルス感染を起こす可能性がある』と指摘して、『危険性を十分に理解し、適切に対応するには医学的知識や技能が不可欠だ』として医師免許が必要だと判断し」て、罰金15万円の有罪判決を下しました。
これは、従来の通説的見解に基づけば、当然の流れの判断だったといえますし、刺青を医療行為から外すと、他の人体に危険を及ぼす恐れのある行為との区別が難しくなり、医師法の規制全体が崩れかねないという判断もあったかもしれません。
また、鍼灸師法が、同じように針を使う施術である鍼師について、わざわざ国家資格を設けているのは、立法者である国会が、上記のような通説的見解を前提にして医師法17条違反の問題をクリアしているともいえますし、厚労省も、「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日医政医発105号通知)、「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」につき医師免許を持たない者が業として行うと医師法17条に反すると通知しているなど、既に上記の通説的見解が定着していて、医師法17条の明確性は問題なくなっているという理解も十分あり得ると思います。
これに対し、控訴審判決は、上記のように、医学の進歩と共に医療行為の概念が周辺に広がって不明確になり、一般国民の医療行為のイメージから乖離し、刑罰規定としても明確性を欠いているのではないか、という問題意識が根幹にあるように思われます。
刑罰法規の明確性は、自分が何をしたら処罰されるのかを国民に明示し、国家による恣意的な刑罰権の行使を防止するための憲法上の要請であり、刑事裁判官であれば、本能的な問題意識かと思います。その意味では、控訴審判決は、そうした問題意識に素直なアプローチですし、刺青が一般的な認識として医療プロパーの行為かそうでないかというところから、医療行為の概念を再構成することも首肯できるところではあります。
ただ、医療行為の定義を医療関係かどうかで区別するとすれば、同義反復となるのでは?という気がしますし、もともと医療の意味や範囲が不明確だからこその問題だとすると、結局、不明確性が解消されるのか?という気もします。特に美容関係の医療行為は、本来の医療そのものではありませんし、同様に針を使うアートメイクの扱いも気になるところです。
今回の裁判は、まさに刑罰法規の明確性が主たる争点であり、おそらく検察は上告するでしょうから、最高裁による統一的な判断が待たれます。
日本経済新聞(2018年11月15日)に「最高裁による統一判断必要:元裁判官の甲斐野正行弁護士の話」として掲載されています。