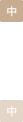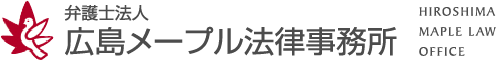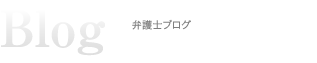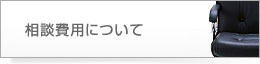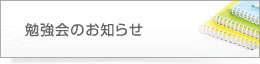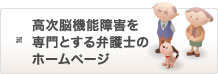「改正債権法拾遺~施行までに整理しておくべきこと①-経過措置その9~法定利率Ⅲ」
2020.02.28|甲斐野 正行
前回・前々回と見てきました「法定利率」については、損害賠償のうち将来得べかりし利益の算定に用いられる中間利息控除にも影響があります。
将来の逸失利益や将来の介護費などは、将来にわたって毎年一定額で発生するものと仮定して計算するわけですが、その一定額にそのまま年数を掛けた額を賠償額として被害者が現時点で一度に受け取ると、被害者はこれを運用することによって生じる利息(中間利息)分だけ過大な利益を得ることになります。
そこで、公平の観点から、将来の損害分については、中間利息分をあらかじめ控除して算出する方法が採られているのです。
この中間利息控除は、現行法では民法に規定がなく、判例上、損害賠償額の算定にあたり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率、つまり、年5%によらなければならないとされたこと(最判H17.6.14民集第59巻5号983頁)から、そのように運用されています。
改正債権法は、これを明文化したわけで(改正法417条の2、722条1項)、その考え方自体は現行法でも改正法でも変わりはないのですが、現行法が適用されるか、改正法が適用されるかで利率が異なります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、一般に不法行為時に発生すると考えられ、遅延損害金も不法行為時の法定利率によることとされています(改正法419条1項)。
もっとも、後遺障害による逸失利益の場合、症状固定時を基準に労働能力喪失期間等を考え、そうすると、不法行為時とは時期が大きくずれることが通常よくあるのですが、遅延損害金が不法行為時の法定利率によることとのバランスから、中間利息控除も、賠償債権が発生する不法行為時を基準にすることとされました(改正法417条の2、722条1項)。
つまり、不法行為が施行日前なら、症状固定が施行日以後でも、現行法の年5%で中間利息控除も計算するということです。
以 上